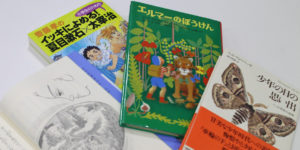あすなろ学習会 責任者・授業担当者のブログです
あすなろ通信
小さな成長 vol. 1
『読み書き教室』担当の古川真子です。
とても嬉しい出来事がありました!
4月から通っていた小学1年生の子どもが,なんと 3ヶ月の間に90冊も本を読みました!!
「90冊も読んだよ!」
と,本人もとても嬉しそうでしたし,私も彼女の成長ぶりに涙が出そうになるほど嬉しく感じました。
90冊まで到達することができた秘訣として,1つ挙げられます。
それは「家族の協力」があったことです。
お母様が忙しいときには,おばあさまが本を読み聞かせしてくれていたそうです。
「おばあちゃんの本の読み方が好き!」
と,いつも楽しそうに話してくれていました。
親の目線から見ると
「うちの子はこんな本しか読まない……。」
「うちの子は本当に本を読んでいるのかしら」
と,不安に思うかもしれません。
しかし,1,2年生は特に自分ですらすらと読める本が限られているため,一人で読むとなると,限られたシリーズの本しか読めない可能性があります。
だからこそ、本来は1冊の本を親子で一緒に読む時間がとても重要になってきます。
でも,仕事をして家に帰って,それから家のことをやって子どものためにと……休む間もなく働いてばかりでそんなことできない!―――と,思う方もきっといらっしゃると思います。
だからこそ,『あすなろ学習会』が第2の家となり,子どもたちと1冊の本を共有しあえる関係をこれからももっと築いていきたいと改めて感じました。
見直しをする
『そろばん暗算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。
『ビジュアル算数』授業では,個々にプリントを解き進めます。
1枚終わるごとに「できました」「お願いします」と,子どもたちが私のもとへ持ってきてくれます。
子どもたちの,よくあるミスが以下の 4点です。
・答えの単位を書き忘れている。または,単位を書き間違えている。
・式は書いてあるのに,式の計算結果が書いてない。(例:28×14= で止まっている)
・計算ミスをしている。
・思い込みで式を書いている。(例:ひき算の文章問題が続いていたため,次の問題もひき算だろうと思い込んでしまう。)
丸つけをしながら,私が「あ,」と呟くと,子どもたちも「あぁ!」と気づきます。
私より先に「あ,しまった!」と気づく子もいます。
私のもとへ持ってきたときには,注意深く自分の解答を見ているので,子どもたちも自分のミスに気づきやすくなります。
学校の単元テストでも「もったいないミスをする」という保護者の方からのお話も聞きます。
「早く終わった」という満足感が強かったり,「見直しをしているつもり」になっていたりすると,自分のミスには気づくことができません。
『そろばん暗算・ビジュアル算数』では,子どもたちが自分で見直す力も育みます。
『そろばん暗算』では,ステージ昇級のためのテストがあります。
この合格基準は全問正解です。
そのため,テスト時間を少し長めに設定しています。
テスト前には「緊張する!」と言う子もいます。
この緊張感も良い練習になります。
テスト中,一通り計算が終わると「終わった」「よし,見直しだ」と呟き,見直しモードのスイッチが入ります。
今までに見たことのない集中力でそろばんの玉をはじきます。
全問正解すると,その達成感からか「やったー!!」と笑顔が見られます。
その後,ほとんどの子が自分から「ここが不安で,何回も見直ししたの!」「 2回目の答えが違ったから、何回も見直した!」と,話してくれます。
また,「まず 1番下の列にある計算を見直して,あとは全部を 2周見直したよ。」と,自分が気をつけたことを話してくれます。
どうしたら全問正解できるか,自分で考えて取り組んでくれています。
『ビジュアル算数』の文章問題でも,「答えに書き間違いがないか」「計算ミスがないか」を確認してから,私のもとに持ってくる子が増えました。
1人では,妥協してしまう見直し。
これからも一緒に見直しに取り組んでいきましょう。
あすなろ学習会の今夏のチラシが完成しました!
『あすなろ学習会』の今夏のチラシが完成しました。
6月に入って以降,入会希望の方からのお問い合わせが増えてきました。
入会をご希望の方は,入会説明会・体験授業をお電話またはインターネットにてお申込みいただきますようお願い致します。
自分で考える
『そろばん暗算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。
学年が上がるにつれて,算数が「きらい」「にがて」という子どもたちが増えてきます。
理由は様々ですが,そのひとつが「文章問題の内容が分からず,どんな式を書けばいいのか分からない」という理由からです。
私自身,小学5年生の頃に『割合』が全く分からず,適当にかけ算したり,わり算したり…。
そのまま復習せずに学年が上がり,中学3年生のときに『割合に関する文章問題』で苦戦し,その時にやっと焦り始めて必死に復習を始めました。
ドリルやテキストには『小数のかけ算』『分数のわり算』などの単元名が書いてあるので,「かけ算でいいや」「これもわり算だ」と判断し,問題文を読み込まずに式を書いてしまいます。
残念ながら,それでは力がつきません。
小学校高学年,中学生と学年が上がるにつれて苦労していきます。
『ビジュアル算数』の授業では,どういうときに『たし算・ひき算・かけ算・わり算』をするのか,図や絵のメモを使って判断する練習をします。
文章問題にはひっかけがあり,『わり算』の単元でも,『たし算・ひき算・かけ算』の文章問題が出てくる構成にしています。
子どもたちは「先生,ここかけ算の問題だね」と気づくようになってきました。
答え合わせをするときに,私が「なぜ,かけ算しようと思ったの?」と聞くと「これはね,同じ数をたくさん集めるのを考えるからだよ!」と説明をしてくれます。
「文章をよく読もう」と気をつけるようになり,少しずつ自分で考える時間が増えてきました。
これからも一緒に頑張りましょうね。
子どもたちの成長 Vol. 2
『読み書き教室』担当の古川真子です。
「カド(漢字ドリル)はめんどくさい!」
子どもたちから,よく聞く台詞ナンバーワンといっても過言ではありません。
漢字を書くことが好きで得意だった私でさえ,カドの宿題はとても嫌いでした。
さらには,怒られないために行なう作業のように,ただこなすだけでした。
これでは,いくら練習しても,いくら頑張っても身につくはずのものも身につきません。
なんとか漢字を書くことが「楽しい!」と思える瞬間を作れないかな…と思い,ある書籍をすべてひらがなで打ち直し,書くことのできる漢字を探す―というプリントを作成してみました。
すると,小学2年生なのに「けしき」という漢字を辞書から探し当て,書くことが出来ていました。
「すごい! よく書けたね!」と褒めると,
「先生,これって何年生の漢字なの?」と聞くので,
「4年生の漢字だよ。」と答えました。
すると,「こんな簡単な漢字なのに!! 2年生でも書けるよ!」と自慢げに話していました。
もう聞いてる私としては,ついつい笑ってしまいます。
また,ただ書くだけでなく,書き順を調べてから正しく書く子や,私にお手本を書かせ,真似してきれいに書こうとする子。
こんな風に辞書を用いて,楽しく漢字の勉強をする小学2年生は『あすなろ学習会』にしかいない!
と,思いながら見守っていました。
他にも,子どもたちが楽しみながら自ら学べるものを,もっともっと考え,もっともっと子どもたちに勉強する楽しさが伝わるといいなと思います。
新学年が始まって
『そろばん暗算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。
新学年が始まり,1ヶ月が過ぎました。
この春から『あすなろ学習会』の仲間になった子たちも,少しずつこの環境に慣れてきたようです。
写真は私が摘んできたカラスノエンドウとスズメノエンドウのさやで,子どもたちは興味津々の様子でした。
この 4月から『あすなろ学習会』に入って初めてそろばんを使う子や,学校でそろばんを少し経験した子など,さまざまな子がいます。
指の動きに慣れることから始め,現在は易しいたし算を練習しています。
まだ 1ヶ月ほどですが,指がスムーズに動いています!
これからはたし算の中でもくり上がりがメインとなり「ちょっと難しいかも」と思うことがあるかもしれませんが,一緒に頑張っていきましょうね。
2年目に突入する子もいます。
授業が始まってからの集中力は「さすが2年目!」と言いたくなるほど,教室内にそろばんの玉の乾いた音が響きます。
丸つけに来たときは,表情もゆるみ,笑顔が見せてくれます。
オンとオフの切り替えができていますね。
最近では「ちょっと暗算に自信がついた」と言ってくれる子たちもいます。
計算は算数の基礎となる力です。
これからも頑張りましょうね!
チューリップ
『そろばん暗算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。
いつもより長く楽しめた桜の花も,散り始めてきました。
外を歩いていると,風が強かったために「この花びらはどこから飛んできたの?」ということもありました。
入口のカウンターにチューリップの花を飾っていたのですが,今日になって花びらが 1枚,2枚…と散り始めました。
授業前,子どもたちと散り始めているチューリップを見ていると,きれいに全部落ちきってしまいました。
「花びらから紫色の汁が出ると思う!」
「先生、ティッシュに色をつけたらいいと思う!」
と,教えてくれた子がいたので,授業が終わってからティッシュを染めてみました。
机の上で叩き染めをしました。
「爪で傷つけてからやるといい!」と教えてくれた子もいました。
グーッと押すのか,速くたたくのか…。子どもたちは思い思いの方法で染めてくれました。
ティッシュに紫色の模様ができ「きれい!」と,ニコニコする子どもたちの笑顔が素敵でした。
6年生の子もやりたいと言って,お迎えがくるまでティッシュを染めていました。
彼は,花びらを揉むようにしてティッシュを染めていました。
入学式
『読み書き教室』担当の古川真子です。
先日の金曜日は,入学式でしたね。
小学1年生になった子どもたち,保護者の皆様,ご入学おめでとうございます。
いよいよ小学生か…と感動しますね。
入学式があったにも関わらず,小学1年生の子どもが元気に塾に来てくれました!
小学校に入学したての頃はまだ字が書けなかったり,助詞の使い方が分からなかったりする時期ですが,自分の意見を書くときにじっくり練習をします。
「を」と「お」の違いが分からず,初めは苦戦していたようですが,「お」が登場すると,どちらで書くべきか,考え書いていました。
よく頑張りましたね!
最近の子どもたちを見て,判断力が年々,低下しているように感じます。
『あすなろ学習会』での学びを通じて,自分の意見をきちんと伝えられる子どもたちを育成していきたいなと思います。
今月末に読書会を行います。
4月は『こどもの日ってなあに?』 と,端午の節句について学ぶ機会にしたいと思っております。
こいのぼりの色は決まっているのか?
柏餅とちまきって何が違うの?
端午の節句って何をする日なの?
端午の節句について,体験したり,調べたりして,楽しく学びます。
今年からの読書会は,『あすなろ学習会』の会員生以外のお子さまも参加することが出来ます。
是非,気になる方はお気軽にお電話ください。
子どもたちの成長
『読み書き教室』担当の古川真子です。
本日は創作発表会に参加していただきまして,ありがとうございました。
あすなろ学習会が昨年から開講し,早くも 1年が経とうとしています。
読み書き教室の 1年間の集大成として,子どもたちに『自分だけのお話』を創ってもらい,その発表会を行いました。
初めは「子どもたちだけで創ることが出来るかな」と,私も心配していました。
しかし,私が思う以上にこんなことまで出来るようになったと,改めて子どもたちの成長を実感しました。
真剣に取り組んだり,
図鑑を使って調べたり,
楽しそうに取り組む姿に,とても感動しました。
子どもたちだからこそ,創ることの出来たかけがえのない作品です。
3月末まで,入り口すぐの本棚に子どもたちの作品を設置します。
子どもたちの作品を多くの生徒や保護者の皆様に,是非ご覧いただきたいと思います。
速算コンテスト
『そろばん暗算・ビジュアル算数』担当の古川由貴です。
本日,『そろばん暗算・ビジュアル算数』を受講している子どもたちが集まり,誰が「速く,正しく計算できるか」を競いました。
『そろばん暗算・ビジュアル算数』は受講曜日選択制のため,この日に初めて会う子もおり,教室内はいつもの授業とは違った雰囲気です。
速算コンテストのルールを伝え,
「始め!」の合図で,一斉にそろばんでの計算を始めます。
計算のレベルは,その子に合ったレベルを設定し,競い合う形です。
合図の後,教室内にはパチパチ,パチパチと玉を弾く音,カツカツと鉛筆で答えを書きこむ乾いた音だけが弾きます。
普段の授業では,分からないことは先生に聞いたりしますので、比較的和やかな雰囲気ですが,今日は全く雰囲気が違いました。
周りの子たちの集中力を感じ取り,「僕も,私も もっと進める!」という気迫に満ちていた空間でした。
昨年に初めてそろばんを習い始めた子たちが,ここまで成長したことに、とても感動しました。
制限時間があと2分,1分と減ってくると,
「このページは終わらせたい」
「この列だけは」
と気持ちが小声になって出てくる子もいました。
タイマーが鳴ると
「終わったー」
と,笑顔も見られました。
採点をしている間は,伊藤先生や真子先生と楽しく過ごしていました。
緊張感がなくなり,収支和やかな時間でした。
結果発表の時間になると,ちょっとドキドキしているようすでした。
結果は
3位 小4生
2位 小1生
1位 小4生
そして,一番多く計算を進めた子は小3生でした。
名前を呼ばれた子に拍手をし,お互いを称え合いました。
嬉しくて自信に繋がった子,悔しくて「次こそは」と思った子,何かを感じたことが次の成長に繋がります。
これからも頑張りましょうね。